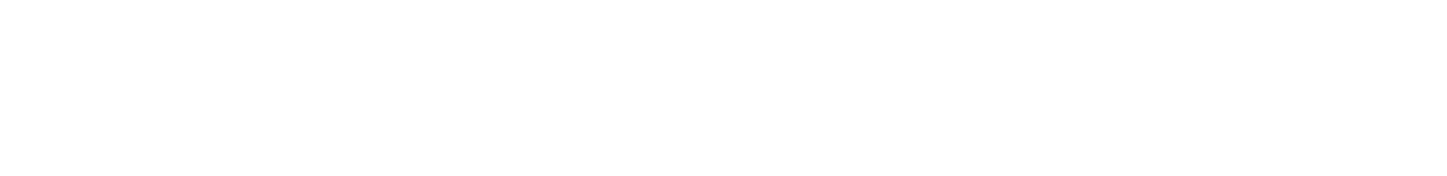仕事をしない同僚はどの職場にもいるようで、「休憩室の番人かのようにずっと休憩している人」、「自分の仕事を人にさせてスマホゲームをする人」、「仕事しているフリをして何にもやっていない人」仕事を真剣にやっている人からすると、イライラしてストレスが溜まってしまいますよね。
この記事で解決できるお悩み
- 仕事をしない同僚にイライラする
- 仕事をしない同僚がストレスの種
- ストレスを回避する方法が知りたい
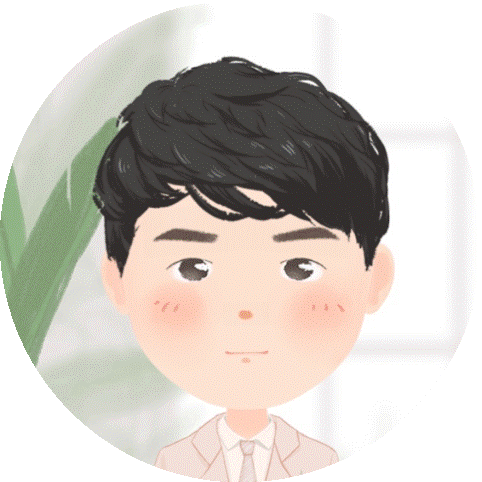
この記事では、仕事をしない同僚に「イライラする」、「ストレスがたまる」という人に向けて、「実際にいた仕事をしない同僚の話」→「仕事をしない同僚にイライラするときの注意点」→「仕事をしない同僚へのイライラ・ストレスの対処法」の流れでお届けしていきます。
もしも、仕事をしない同僚へのストレスが限界をむかえそう...というときは、▼こちらの記事を読んでみてください。
合わせて読みたい
-

-
「もう疲れた、人生休みたい」というときの教科書|おすすめする人生の休み方
2025/10/1
働いていると「もう疲れた、人生休みたい」と思ってしまうときがありますよね。わずらわしい職場の人間関係や忙しすぎる仕事、理不尽な上司からのパワハラ。人生に疲れてしまって「しばらく人生をお休みしたい」とい ...
-

-
退職後しばらく休みたいという人へ1年間お休みした体験を語ります。
2025/10/6
ここまで耐えたんだから、退職してからしばらく休みたい!というその気持ち、ものすごく分かります。山のような仕事量に押しつぶされそうになったり、職場の人たちとうまくいかなくて逃げ出したくなったり。人生は長 ...
仕事をしない同僚の特徴と心理

まずはじめに、仕事をしない同僚の特徴とその心理についてお話ししておきたいと思います。仕事をしない同僚には「そもそも仕事量の基準が違うタイプ」、「責任感が薄く「人任せ」にするタイプ」、「上司や周囲が甘やかしているケース」があります。
そもそも仕事量の基準が違うタイプ
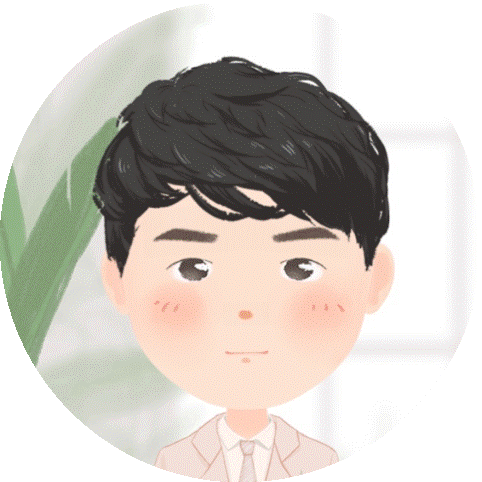
こうした同僚は、本人の中での「仕事の基準が低い」ため、こちらからすれば「仕事をしない同僚」と映ってしまい、イライラの原因になります。例えば、自分が時間内に5つの業務を片づけているのに、相手は2つで満足している…そんな状況が続けばストレスも溜まりますよね。
悪気がない分、注意しても改善されにくいのも厄介です。あなたの努力や基準と比べてしまうと不公平感が募りますが、大切なのは「自分はどう成長したいか」に意識を向け直すことです。基準の違いに振り回されすぎないことで、少しでもストレスを軽減できるはずです。
責任感が薄く「人任せ」にするタイプ
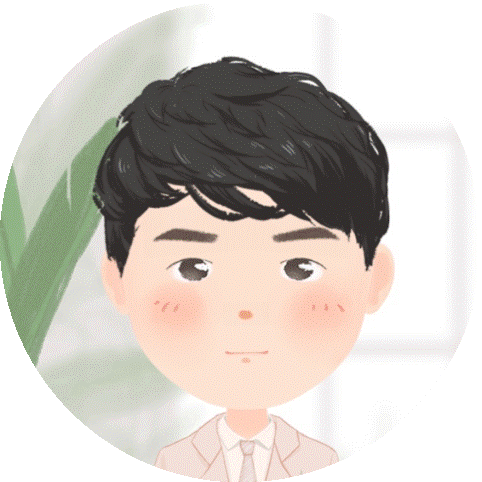
こうしたタイプは、締め切りが近づいても焦らず、結果的に周囲がカバーせざるを得なくなることもしばしば。そのたびに「なぜ自分ばかりが負担を背負わなければならないのか」とイライラが募っていきます。特に真面目で責任感の強い人ほど、こうした態度に耐えられなくなりがちです。
放置すれば、あなたのモチベーションや健康にまで悪影響を及ぼします。仕事をしない同僚にストレスを感じたときは、まず「自分の役割」と「相手の役割」を切り分ける意識が大切です。必要なら上司に報告し、業務の偏りを改善してもらうのも一つの手段です。自分だけが抱え込まない工夫が、心を守る第一歩になります。
上司や周囲が甘やかしているケース
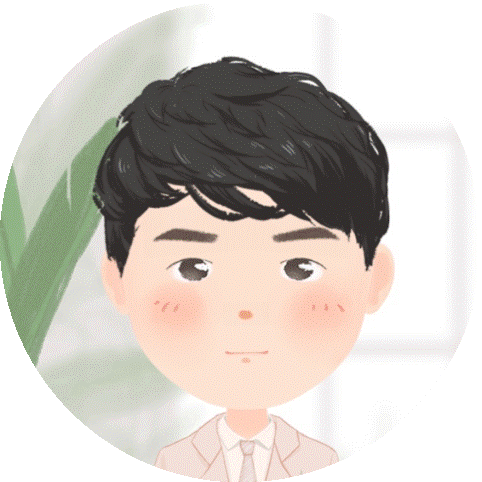
本来なら注意されるべき行動が見逃されていると、本人は「これでいい」と思い込み、怠け癖が固定化してしまうのです。その結果、真面目に働いている人だけが余計な負担を背負い、イライラやストレスを感じる悪循環に陥ります。特に上司が「仕方ない」、「あの人はそういうタイプだから」と見て見ぬふりをしていると、現場の不満はますます大きくなりますよね。
そんなとき大切なのは、「自分一人で解決しようとしない」ことです。上司や人事に状況を伝えたり、信頼できる同僚と問題を共有したりすることで、あなたのストレスは確実に軽減されます。我慢し続けるより、声を上げる勇気が必要です。
仕事をしない同僚—実働2時間の男―【実録】
実際に存在した仕事をしない同僚、実働2時間の男の名前は小沢さん(仮名)。この同僚は上司に怒られても変わることなく、あの手この手を使って就業時間7.5時間の会社で実働2時間をなしとげていきます。
かつて私は、小沢さんと2人で同じ仕事を担当していました。その時の小沢さんの仕事のサボり方を紹介していきます。
①トイレから長時間戻らない

仕事をしない同僚のサボり方の一つ目は、「トイレから長時間戻らない」です。むしろ「トイレに長時間こもる」この表現が正しいくらいでした。小沢さんは社用携帯電話の電源を切って、1日に2時間くらいはトイレにこもるんです。
もう、トイレにパソコンとデスクを設置してあげたくなってしまっていました。
ちなみに、トイレから離れられない病気の方もいらっしゃいますが、小沢さんの場合は単なるサボりでした。こんな仕事をしない同僚にはイライラしてストレスが溜まっていますよね。
②オフィスから遠い休憩所を使う

仕事をしない同僚のサボり方の二つ目は、「オフィスから遠い休憩所を使う」です。小沢さんは上司に長時間休憩しているのがばれないように、自分のオフィスから遠い他部署の休憩所で1~2時間休憩していました。
もう帰り道を忘れて、迷子になって欲しいくらいでしたね。
③いつもスマホで遊んでいる

仕事をしない同僚のサボり方の三つ目は、「スマホで遊ぶ」です。小沢さんはオフィスにいても、仕事する振りをしながら机の下でこっそりスマホゲームするか、SNSを見てるんです。小沢さんはおそらくスマホ依存症で、職場の電子機器持ち込み禁止エリアに行くときも手放せずに、そこでSNSを見ていて、上司にスマホを没収されたことがあるほどです。
彼は、スマホを開発した人に心から感謝して、お礼の手紙を書いたほうがいいと思います。
④暇なくせに忙しいフリをする

仕事をしない同僚のサボり方の四つ目は、「忙しいフリをする」です。小沢さんは大した仕事もないくせに、難しい仕事が来ると急に忙しいフリをするんです。どんな仕事を抱えているか聞いてみると、10分もあれば終わるような仕事。10分で終わる仕事を何時間もかけて終わらせるのは、それもそれでさぞ辛かったことでしょう。
⑤退社時間だけは絶対に守る

仕事をしない同僚のサボり方の五つ目は、「退社時間は必ず守る」です。ただでさえ仕事をしなくて、私が小沢さんの分の仕事までやっていたわけですが、ほぼ二人分の仕事ですから定時までに終わるわけがありません。だけど、小沢さんはどんなに仕事が残っていても定時でこっそり帰ります。いつ帰ったのか分からないくらいこっそりと。
⑥3日に一回は遅刻する

仕事をしない同僚のサボり方の六つ目は、「3日に一回は遅刻する」です。ウソみたいな話ですが、本当なんです。その会社にはタイムカードがなかったので、労働時間は自己申請すればよくて、仕組み上、遅刻・早退という記録が残りません。その裏をかいた犯行か、本当に連続寝坊のポンコツだったのかはわかりませんが...
この6つの方法を組み合わせれば、実働2時間なんて余裕でなしとげられます。当然、小沢さんは毎日上司に怒鳴られていましたが、それでも懲りずに実働2時間を実現する男。ここまで仕事をしない同僚にはさすがに、イライラしてストレスが溜まってしまうのも無理はないでしょう。
仕事をしない同僚にイライラするときの注意点

ここで、仕事をしない同僚にイライラするときの注意点として、私が実際に試してみて失敗だった方法を紹介します。これをやってしまうと、イライラが増していくか、イライラの対象がかわるだけですから、残念ながら根本的な解決はできずストレスが溜まる一方でした。
注意点
- 同僚の意識を変えようとしない
- 上司にどうにかしてもらおうとしない
- 配置換えをしてもらっても意味がない
注意点①:同僚の意識を変えようとしない
仕事をしない同僚の意識を変えようとするのはイライラが増してしまうだけでした。
なぜなら、仕事をしない同僚に注意しても、お願いしても、頑張っている姿を見せつけようと、人の意識は簡単には変えられないからです。
だから、「何回も言ってるのに何で分からないんだ!」「こんなに負担がかかってるのに何で平気なの?」こんな風にイライラが増してストレスがたまってしまうだけでした。
数回注意しても変わらないときは、自分のためにも同僚の意識を変えようとすることはやめたほうがいいでしょう。
注意点②:上司にどうにかしてもらおうとしない
仕事をしない同僚を上司にどうにかしてもらおうとするのは良い方法とは言えません。
なぜなら、たとえ上司が同僚に注意したり、罰を与えたりしたとしても、同僚が心を入れ替える保証はどこにもなくて、イライラの矛先が上司に向かってしまうだけだからです。
矛先が上司へ...
- 同僚がまだサボるのは上司のせい
- 上司は部下の管理ができていない
- 上司は私の大変さが分かってない
相談するのは全然問題ありませんが、相談したから上司がどうにかしてくれると思ってしまうと、結局イライラの対象が上司に変わるだけで、ストレスは変わらずたまってしまいます。
注意点③:配置換えをしてもらっても意味がない
仕事をしない同僚にストレスの限界で、配置換えをしてもらうのは一見良さそうに見えますね。
だけど、結局は他の同僚の手抜きが目について、イライラの矛先が他の同僚に変わるだけでした。
なぜなら、人が入れ替わってもサボる人はどの組織にも一定数は存在するからです。「働きアリの法則(2:6:2の法則)」が本当かどうか分かりませんが、間違いなく今まで目につかなかった人のサボりが目につくようになります。
働きアリの法則
組織では、よく働く人と、普通に働く人と、ずっとサボっている人の割合は、2:6:2になる。
もしも、仕事をしない同僚へのイライラ・ストレスに耐えられそうにない...というときは、▼こちらの記事を読んでみてください。
仕事をしない同僚へのイライラ・ストレスの対処法

結局、どうしたら仕事をしない同僚へのイライラ・ストレスを回避できたかというと、自分の脳と向き合うことに限ります。仕事をしない同僚にイライラさせられていると思っていても、本当はイライラしているのは自分の脳ですから。
対処法
- 意識を自分に向けてみる
- 自分の信念を疑ってみる
- 仕事を重要なものから外す
対処法①:意識を自分に向けてみる
仕事をしない同僚へのイライラ・ストレスを回避した一つ目の方法は、意識を自分に向けてみることです。
仕事をしない同僚にイライラしたとき、それまでは、「なんでこいつは仕事をしないんだよ!」と、意識はその同僚に向いていました。
その意識を自分に向ける。
・あ、今自分は怒っている
・今、イライラしているな
・何で怒りが湧くんだろう
そうすると、仕事をしない同僚にイライラさせられているというよりは、自分の脳内で怒りが湧きおこっていることを改めて実感します。
この、意識を自分に向けてみることが、仕事をしない同僚へのイライラ・ストレスを回避するための第一歩だったように感じますね。
対処法②:自分の信念を疑ってみる
仕事をしない同僚へのイライラ・ストレスを回避した二つ目の方法は、自分の信念を疑ってみることでした。
| 信念 | 疑う |
| 仕事中は仕事に集中しなければならない。 | 嫌な仕事のために無理して体を壊すくらいなら、サボりながら自分のペースでやったほうがいいのかもしれない。 |
| 仕事の量に見合った給料であるべき。 | 会社全体から見たら自分と同僚の仕事量に大した差はないのかもしれない。それに、仕事が多ければそれだけ経験値は上がるから、得してる可能性もある。 |
| 仕事を頑張るのは当たり前。 | 仕事で成功したい人は仕事を頑張るのは当たり前だけど、そうじゃない人からしたら頑張らないのが当たり前。 |
イライラしたときを思い返してみると、大なり小なりの自分の信念に相手が反してしまっています。「○○するべき」「□□しないといけない」「△△するのは当たり前」これは、ほとんど自分が作り出しています。
自分が正しいという思い込みを疑ってやることで、仕事をしない同僚へのイライラ・ストレスをある程度回避することができました。
対処法③:仕事を重要なものから外す
仕事をしない同僚へのイライラ・ストレスを回避した三つ目の方法は、仕事を重要なものから外すことでした。
人は目や耳には入っていても、その人にとって重要なものしか見たり聞いたりしていません。正確にいうと重要なものしか意識上にあがらないようになっています。
たとえば...
- 同僚にこの髪型どう思う?って聞かれたけど、言われるまで同僚が髪を切ったことに気づかなかかった。
- 通勤するときにいつも通っている道だけど、今日の飲み会で来るまで、ここに居酒屋があることに気づかなかった。
- 明日のデートを楽しみに思う気持ちが強すぎて、今日は多少イヤなことがあっても全然気にならない。
このように、自分が無意識的に重要だと思っていること以外は、気にならないようになっています。裏を返すと、仕事を重要なもの以外に分類することで、職場で多少嫌なことがあっても気にならないようになるということです。
そこで、私は仕事に全く関係ない資格の学習をすることにしました。すると、仕事中も暇さえあればその資格のことしか考えていないから、自然と仕事をしない同僚のことなんてどうでもよくなっていきましたね。
仕事をしない同僚にストレスを溜めない心の持ち方

ここまで、仕事をしない同僚へのイライラ・ストレスの対処法について、私が実際にストレスを回避した方法をもとにお伝えしてきました。ぜひ、あなたにもストレスを回避して欲しいと願っています。ここでは、仕事をしない同僚にストレスを溜めない心の持ち方をお伝えしていきます。
「自分の成長」に意識を向ける
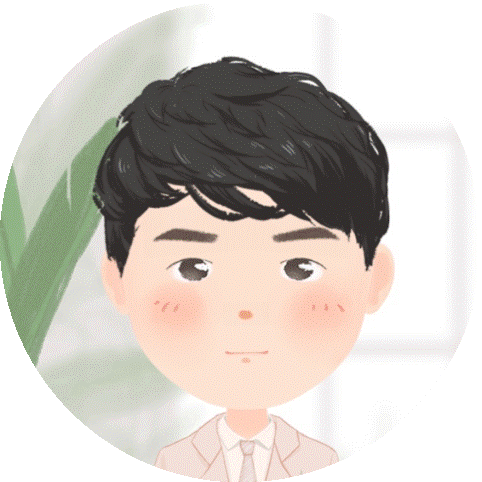
その気持ちはとても自然なものです。しかし、ずっと他人の行動に振り回されていると、ストレスばかりが溜まってしまいます。そんなときに大切なのは「自分の成長」に意識を切り替えることです。
たとえば、同僚がやらない分をカバーすることで、あなたのスキルや経験が人一倍磨かれると考えてみましょう。もちろん理不尽さは残りますが、「この経験は将来必ず自分の武器になる」と思えば、イライラを前向きな力に変えることができます。
他人を変えるのは難しいですが、自分の捉え方を変えることはできます。努力を無駄にせず、自分の成長へとつなげることで、ストレスを少しずつ和らげられるのです。
職場は仲良しクラブではないと割り切る
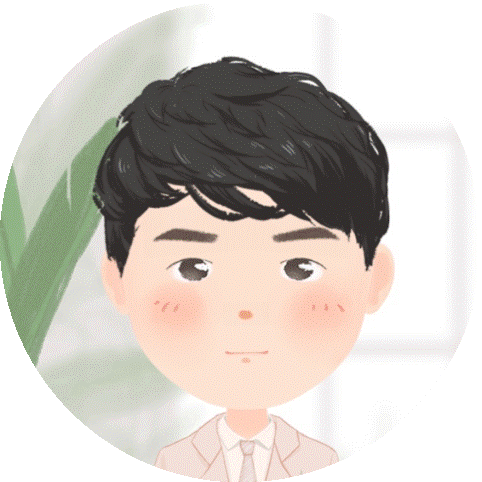
中には責任感が薄く、仕事をしない同僚もいますし、そのことでイライラやストレスを感じるのは当然のことです。ただ、職場はあくまでも「仕事をする場所」であり、仲良しグループを作ることが目的ではありません。
そう割り切ることで、余計な期待をせずに済みます。仲良くする必要も、無理に関わる必要もないと考えると、心がぐっと軽くなるはずです。あなたが本当に大切にすべきは「業務をしっかり遂行すること」と「自分の生活や健康を守ること」です。
無理に同僚と歩調を合わせようとせず、割り切って距離を取ることで、イライラを減らしストレスを抱え込まない働き方ができます。
趣味やプライベートでストレスを解消する
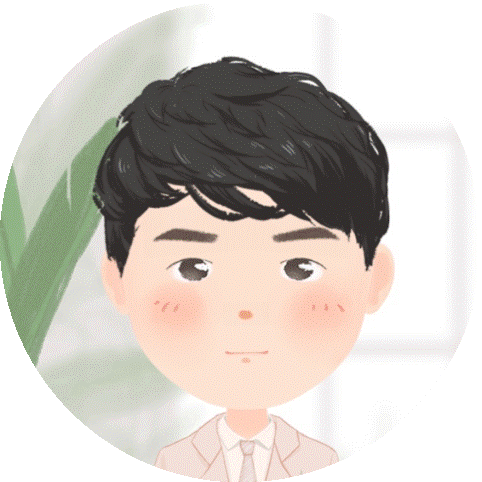
そのイライラを職場で抑え込むだけでは限界がありますから、プライベートでうまく発散することがとても大切です。趣味に没頭したり、好きな音楽を聴いたり、運動で汗を流したりすると、心に溜まったモヤモヤが少しずつ薄れていきます。
また、信頼できる友人や家族に「実は仕事をしない同僚がいて…」と打ち明けるだけでも、驚くほど気持ちが軽くなるものです。職場で感じたストレスは、職場の中だけで解決しようとすると苦しくなります。
だからこそ、自分の生活の中に「リフレッシュできる時間」を積極的に作ることが必要なのです。仕事でのイライラをプライベートで上手に解消すれば、翌日からまた前向きに働く力を取り戻せますよ。
もしも、仕事をしない同僚へのイライラ・ストレスに疲れちゃった...というときは、▼こちらの記事を読んでみてください。
仕事をしない同僚へのストレスが限界なら環境を変える選択肢も

ここまで、仕事をしない同僚にストレスを溜めない心の持ち方をお伝えしてきました。ここでは、仕事をしない同僚へのストレスが限界なら環境を変える選択肢も大切ですよということをお伝えしていきます。あなたには、安心して働ける環境を選ぶ権利がありますから。
異動願いや転職を視野に入れる
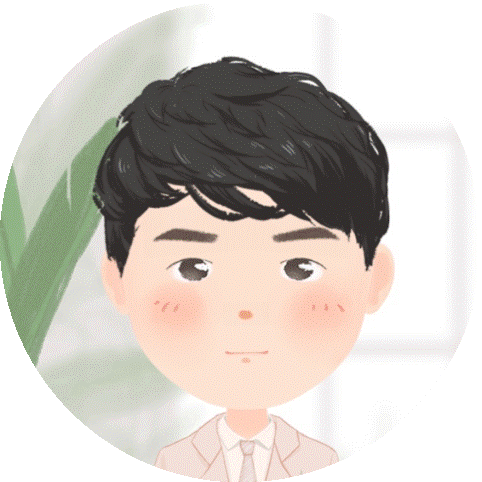
そのようなときは、自分を守るために「環境を変える」という選択肢を持つことも大切です。まずは、社内で異動願いを出すことを検討してみましょう。部署が変わるだけで、人間関係や仕事の雰囲気が大きく変わり、驚くほど働きやすくなるケースもあります。
もし異動が難しい場合や、会社全体の風土が合わないと感じるなら、転職を視野に入れるのも一つの方法です。「辞めたら負け」などと考える必要はありません。むしろ、あなたの健康や未来を大切にする前向きな決断です。仕事をしない同僚にストレスを感じ続けるよりも、新しい環境で自分らしく働ける道を選ぶことは、人生にとって大きなプラスになります。
働きやすい環境を選ぶことも自分を守る手段
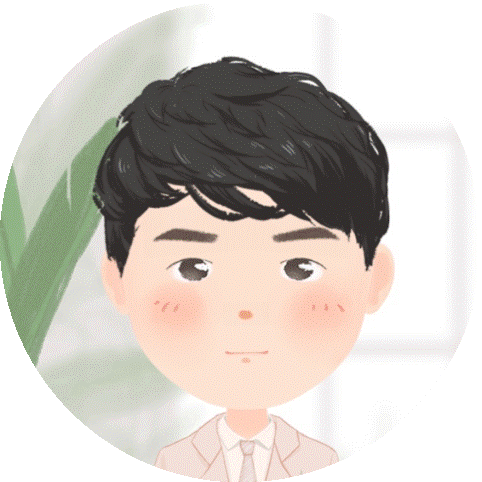
そんなときに忘れてはいけないのは、「自分が安心して働ける環境を選ぶ権利がある」ということです。今いる会社や職場がすべてではありません。世の中には、自分の努力を正当に評価してくれる職場や、仲間と協力して働ける環境がたくさんあります。
無理をして今の職場にとどまり続けることが、必ずしも正しい選択ではないのです。転職活動を始めるだけでも、「いざとなれば動ける」という安心感が得られ、仕事をしない同僚に振り回されるストレスが軽減されることもあります。
自分に合った環境を選ぶことは、逃げではなく、自分を大切にする前向きな行動です。働きやすさを優先することで、人生はもっと豊かに、心穏やかに過ごせるようになります。
まとめ:仕事をしない同僚に振り回されず、自分を大切に

職場で仕事をしない同僚がいると、どうしてもイライラしたり、余計なストレスを抱えてしまいますよね。真面目に働くほど、「なぜ自分ばかり頑張らなきゃいけないのか」と不公平感が募るのは当然のことです。
しかし、同僚の行動そのものを変えるのは難しいため、まずは自分の心の持ち方を工夫することが大切です。「自分の成長に集中する」「職場は仲良しクラブではないと割り切る」「プライベートでリフレッシュする」など、小さな工夫を積み重ねることで、ストレスを軽減できます。
それでも、どうしても我慢の限界を超える場合には、異動や転職といった「環境を変える選択肢」を考えるのも自分を守る大切な手段です。無理に耐え続ける必要はありません。大切なのは、どんな状況でも自分らしく、安心して働ける環境を見つけることです。仕事をしない同僚に振り回されるのではなく、自分の未来を大切にする選択を重ねていきましょう。
仕事をしない同僚にイライラしていると、仕事・会社・人生が嫌になってしまいますから、この記事が少しでもあなたの力になれることを願っています。